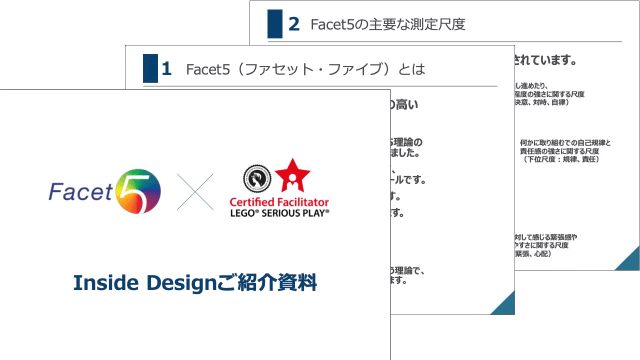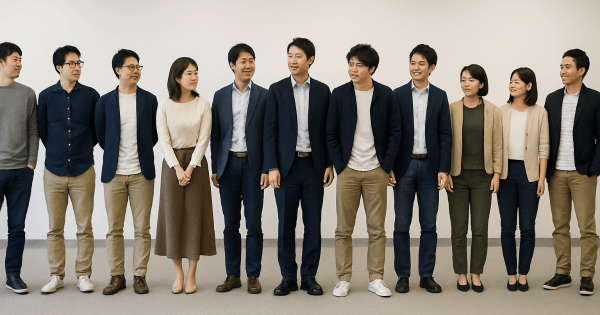東:本日はよろしくお願いいたします。昨年12月にFacet5とレゴ®シリアスプレイ®を活用したワークショップを実施させていただきましたが、今回は特にFacet5を導入する前後でどのような変化があったか、率直にお聞かせいただければと思います。まず、御社の事業概要と組織について簡単にご紹介いただけますでしょうか?
坂谷:はい、改めてプライムプラネットエナジー&ソリューションズの坂谷と申します。弊社は車載用蓄電池などのエネルギーデバイス供給に加え、ソリューション提供を目指している会社です。2020年創業で、グループ全体で約9,000人の従業員がいます。私の部署は生産本部に所属し、グローバルな生産工場の展開企画・プロジェクト推進を担っています。チームは大きく3つあり、海外からの出向メンバーもいるため、英語ネイティブの方々もいます。パナソニックとトヨタの合弁会社という背景に加え、キャリア採用で入社したメンバーも多く、国籍も多様な、まさに「多様性」が特徴のチーム構成です。
Facet5導入前に抱えていた課題
東:ありがとうございます。では、Facet5導入前の課題についてお聞かせください。どのような課題や悩みがありましたか?
酒井:そうですね、私が担当する(3つのグループの一つである)GBX1グループも、坂谷さんがおっしゃる通り多国籍で社歴も様々なメンバーが集まっています。年齢層も幅広く、定年後に再雇用された方もいるため、世代間ギャップも大きかったですね。普段の会話だけでは、それぞれの考え方や思考がなかなか分からず、踏み込んだ会話ができていなかったと感じています。皆が互いの人となりを知らずに一つの仕事を進めているような状況でした。
東:業務上のお付き合いはあっても、それ以上の深いコミュニケーションは少なかったということでしょうか?
酒井:飲み会はありましたが、やはり世代や性別が近い人同士で集まることが多かったですね。
東:マネジメントの立場から見ていかがでしたか?人となりが分からないことで、難しさを感じる部分はありましたか?
酒井:はい、人となりや経験値が分からないことで、仕事が属人化しがちでした。そうなると、さらにコミュニケーションが取りにくくなるという悪循環に陥っていたので、どうにか改善したいと考えていました。
導入を決断した理由と経緯
東:なるほど。では、Facet5を導入することになった経緯や、その時に期待されていたことをお聞かせいただけますか?
坂谷:以前、東さんに別のチームでファシリテートしていただいた経験があったので、そのご縁でご相談しました。私は既存のプロジェクトに新しい部署としてジョインした形だったので、何かいつもと違う形でコミュニケーションを考える時間を取りたいと思っていました。当初はシンプルに「仲良くなる時間」が取れればと思っていましたが、東さんからレゴ®シリアスプレイ®だけでは抽象的になりがちなので、Facet5のように定量的な指標を持てるものと組み合わせるご提案をいただき、チャレンジしてみようと。
東:坂谷さんは事前にFacet5診断のトライアルも受けられましたよね。受けてみて、改めて導入しようと思われた決め手はありましたか?
坂谷:はい。「取扱説明書」のように使える点が非常に良いと感じました。これをオープンにすることで、チームにとって良い場作りの判断基準になると思ったんです。
東:他にもアセスメントツールがある中で、Facet5を選ばれた決め手はなんでしょうか?
坂谷:比較検討はしました。世の中には様々な特性診断ツールがありますが、レゴ®シリアスプレイ®とセットで企画することが前提だったので、東さんとの会話の中でFacet5が最適だと判断しました。
東:導入プロセスや社内への展開はどのように進められましたか?特に、酒井さんのような現場のメンバーへの説明や説得は大変だったのではないでしょうか?
酒井:メンバーのことをもっと知る必要があると感じていたので、坂谷さんがアプローチ方法をよくご存知だったのは助かりました。「こんなツールがあるよ、レゴも使ってとっつきやすいからどう?」という話でしたね。
坂谷:経緯を振り返ると、この部署に来るよりもっと以前にトライアルをご紹介いただいていました。レゴ®シリアスプレイ®も良いと思っていたので、せっかくなら自分のチームだけでなく酒井さんのチームも一緒にやりたいと思い、打ち合わせをしました。レゴ®シリアスプレイ®がどんなものかという地ならしをし、私の決裁金額を超えていたので、上司の杉浦にも取り組みの背景を説明し、実際にワークショップにも来てもらいました。
東:(グループ長であり、お二人の上司でもある)杉浦部長の反応はいかがでしたか?
坂谷:杉浦とは普段から近い距離で話していたので、特に抵抗はありませんでしたね。「投資対効果は?」といった反応もなく、「いいんじゃない?」と(笑)。杉浦自身もコミュニケーションや人材育成の場を重視する方針だったので、ブレーキがかかることは一切ありませんでした。
酒井:私もこの部署に来るまでそういった経験がなかったので驚きましたが、杉浦部長にもそういった背景があったのですね。すんなり進んで良かったです。
Facet5の実施と初期反応
東:ありがとうございます。では、実際にFacet5を活用してみて、どのような効果や変化がありましたか?チームやメンバーの理解度、1on1での活用などについてお聞かせください。
酒井:Facet5の診断結果は紙で出てくるのですが、メンバーの了解を得て、誰でも見られる場所に置いています。メンバーがそれを見ているかは分かりませんが、「あの人は基本的にこういう考え方をする人なんだな」というのが分かるようにしています。診断を受けたメンバーからは「すごく良かった」というフィードバックをもらいました。
坂谷:私も参加者から「やって良かった」という声をもらいましたね。人はつい「あの人はこういう人だろう」とバイアスで決めつけがちですが、診断を受けてみると「ああ、実はこういう特性の人だったんだな」と。普段のその人の行動も、診断結果に書かれていることとつながるな、と納得することがありました。
東:1on1の時などに活用されることもありますか?
坂谷:片手に置きながら、とまではいきませんが、「この人はメッセージを発信したい側なのか、受けたい側なのか」といった参考にしています。チーム内でのメンバー間の会話がうまく進んでいないと感じた時に、「こういう関係性だから、それは難しいだろうな」と推測するヒントにもなりますね。
酒井:1on1の時もそうですが、あえて文字にして書いてあるので、改めて「そうそう、こういう人だよね」と頭に入ります。もちろん1on1では様々な話をしますが、文字化されたものを見るのは非常に良いと思います。
東:文字があることの優位性についてですが、お互いが同じ文字を見ることで共通認識を持てる、という意味合いが強いでしょうか?
酒井:そうですね、その通りだと思います。
東:お二人の上司である杉浦部長とのコミュニケーションにおいて、Facet5の結果が何か変化をもたらしたことはありますか?杉浦部長は「意志」のスコアが非常に高かったと記憶しています。
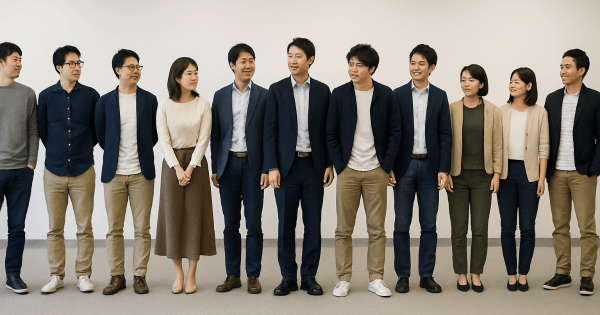 ワークショップでの「ラインダンス」のイメージ画像
ワークショップでの「ラインダンス」のイメージ画像坂谷:私の場合、杉浦部長が私をどう認識しているか、私が杉浦部長をどう想像しているか、その診断結果と想像がほぼ合っていたので、大きく変化があったわけではありません。ただ、ワークショップで皆で並んでバランスを見た「ラインダンス」というワークはすごく良かったですね。
酒井:はい、写真も撮りましたし、あれは本当に良かったです。
坂谷:私と杉浦、酒井と杉浦という1対1の会話というよりは、チームとして互いに思いを馳せることができたと感じます。
酒井:部長が同じことをやって、Facet5の結果を同じ棚に置いているというのは、なかなか無いことだと思います。
東:ラインダンスのワークで、特に何が良かったですか?
酒井:チームとして偏りがある、例えばリーダークラスはこういう特性、担当者はこういう特性、といったことが如実に現れて、改めて分かりやすかったですね。
坂谷:みんなでワイワイ言いながらできたのが良かったと思います。
Facet5がもたらした変化
東:ありがとうございます。Facet5の導入を通じて、組織文化や皆さんのマインドセットに変化はありましたか?対話の質が変わったとか、自分と他者の違いに寛容になったとか、何か感じられた部分はありますか?
酒井:マインドセットまで変化したかは分かりませんが、Facet5のワークショップをきっかけに会話が始まり、コミュニケーションの機会は増えたと感じています。
坂谷:私が後からジョインした立場なので直接的な因果関係は測りかねますが、酒井さんがコミュニケーションが増えたと感じてくださったのであれば、何かしら影響があったのだと思います。特に若い女性メンバーなどは、「あ、〇〇タイプなんですね」といった会話のきっかけになっていましたね。
東:会議での発言や受け入れ方、役割分担の明確化などはいかがでしょうか?
坂谷:全てをFacet5の結果と照らし合わせて解釈しているわけではありませんが、会議の運営などで、ファシリテーターや進捗フォローの役割がうまくハマっていると感じることはあります。それが診断結果に合致していると感じる一方で、結果を読んだからこそそう振る舞っているのかは分かりかねる部分もありますが。
酒井:Facet5の診断結果をもって担当業務を入れ替えたり、というところまではしていませんね。
Facet5の適用が有効な場面
東:ありがとうございます。では、Facet5はどのような組織や課題を持つ企業に特に向いていると感じられましたか?逆に合わないと感じるケースがあれば教えてください。
酒井:私はやはり、異なる文化や年齢の人たちが集まった時に、互いのことを理解できる仕組みとしては非常に良いと思います。古くからある組織でも、改めて診断することで活性化につながる可能性もあるかもしれません。
坂谷:私の感覚では、新しいチームが組閣されたり、私たちのようにプロジェクトという時限組織で集まった際に、まずお互いを知るという意味合いで活用するのは非常に有効だと思います。
酒井:そうですね。プロジェクトで集められて「じゃあ、やってね」となる状況では、非常に有益でしょう。
東:お二人の立場だとプロジェクトメンバーを選定する機会もあるかと思いますが、その際にFacet5のデータがあれば反映される可能性はありますか?
坂谷:人事権まで持たせてもらえるケースは少ないので、アサインされたメンバーが前提ですが、最近Facet5の結果を受けて感じるのは、プロモートしてくれる人がいると仕事がやりやすいということです。新しい部署に異動してチームビルディングを行う際、自分がふわっとしたことを言ってしまうことに対して、実務に落とし込んだり、スケジュールをコントロールしてくれる人がいると、きっと仕事がやりやすいだろうと感じるようになりました。メンバー集めの際の切り口、参考にはなると思います。
酒井:私も同じく人事権は難しいですが、知らない人がどんな人かという時に、距離感を縮めるという意味では非常に有益だと感じます。
今後の活用と展望
東:ありがとうございます。今回、昨年12月に導入されたとのことですが、このタイミングで導入しようという決断のポイントはどこにありましたか?
坂谷:私は新しい部署にジョインしたイメージでいたので、コミュニケーションの質や量について考える時間を取りたいと思っていました。予算もプールされていたので、この年度内にぜひやろうと。
酒井:私はコミュニケーションに課題があると感じていたので前向きでした。杉浦部長の視点からすると、チームの流動性も踏まえ、同じ居室にいるメンバーと一緒に行った方が良いという考えもあったのかもしれません。
東:ありがとうございます。では、導入を検討している他社の担当者さんに対して、勧めるとしたらどんなメッセージがありますか?
坂谷:プロジェクト型の仕事が増え、人材の流動性が高まっている現代において、年上の部下を持ったり、様々なバックグラウンドや制約を持つ方々と働くケースは多いと思います。そういった多様なチームで働かれている方には、一度トライされても良いのではないでしょうか。ただ、上司の承認を得る際に「費用対効果は?」といったフィードバックが来る可能性もあるので、そこを乗り越えるのは大変かもしれません。
東:では、もしFacet5を導入していなかったら、今のチームや組織はどのような状態だったと思いますか?
酒井:チーム力というものは数字で現れませんが、導入しなかった場合に比べたら、確実に上がっていると思います。導入していなかったらコミュニケーションなどに関して、そのまま現状維持だったのではないでしょうか。
坂谷:そうですね。
酒井:坂谷さんのチームとのコミュニケーションも、元々なかったわけではありませんが、Facet5を通して「あの時どうでしたよね」といった会話も増えましたね。距離感が近くなったと感じます。
東:ありがとうございます。最後に、今後Facet5の診断結果をどのように活用していきたいか、もしあればお聞かせください。例えば、新たにメンバーが組織に入ってきたらFacet5をやって全員で共有するなど。
酒井:新しく入ってきた人のFacet5の結果は知りたいですね。もう一度みんなで集まってワークショップをするイメージでしょうか?
東:はい、新しい方がFacet5を受けて個別にフィードバックを受け、それを元にチームで集まって診断結果を共有するワークショップも考えられますし、レゴ®シリアスプレイ®だけを活用する方法など、様々な手法があります。
坂谷:そうですね、やって良かったというフィードバックもありましたし、新しくメンバーがジョインする予定も見えていたので、またFacet5なのか、別のツールになるかは分かりませんが、そういった時間を予算をつけて行いたいと考えています。今年度の予算にも盛り込んでいます。私自身は別の部署に異動してしまうのですが、次の部署の上司には、とりあえず私の「取扱説明書」としてFacet5の結果を渡しました(笑)。
酒井:(笑)もう渡したんですか?
坂谷:はい、チャットでデータも送りました。上司からはびっくりマークが返ってきましたが(笑)。自己開示に使えると思いますし、新しいチームでもまたチームビルディングの時間が持てると良いなと思っています。
東:新しい上司の方の反応はいかがでしたか?
坂谷:びっくりマークが返ってきましたね(笑)。私の上司も雑談を大事にする方なので、比較的理解を示してくれています。
酒井:やはりその時に一緒にやるからこそ、一体感が生まれるのだと思います。「私のFacet5診断の結果はこれです」とだけ言われても、驚く反応になってしまうかもしれません。
坂谷:私もそう思います。テストに回答して紙だけもらっても、あまり見ない気がしますね。
東:そうですよね。書いてあることも解説がなければ難しい部分もありますし。ちなみにFacet5は、人の性格を程度の問題と捉える「特性論」に基づいています。良いも悪いもなく、グラデーションの中で個々の特性を理解するという考え方です。企業が導入する診断には「タイプ論」が多いですが、Facet5のような詳細な特性論の方が、より深く個人を理解できるというメリットがあります。